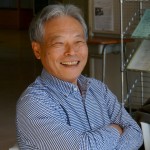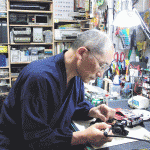新しい国分寺市プレイステーションにできた
外遊びもできる親子ひろば

戸倉通りから見えるプレイステーションの建物
国分寺市プレイステーションが西元町から東戸倉に移転しました。新しいプレイステーションには、2階建ての建物が あります。この建物の2階に親子ひろばBOUKEN どんどこができました。親子ひろばとは、主に0歳~3歳の子どもと保護者が来て、遊ぶ、他の利用者とおしゃべりする、地域の情報を得る、子育ての悩みを相談する、などができるところです。
BOUKEN どんどこは、国分寺市からの委託を受けて、認定 NPO 法人冒険遊び場の会が運営しています。 「プレイステーションは外遊びを主とする場所なので、今まではお子さんが歩けるようになってから遊びに来る人がほとんどでした。新しいプレイステーションは親子ひろばが併設されたので、生後1か月から利用可能です」と、BOUKEN どんどこ責任者の塩原真有美さん。
 階段上って正面が BOUKEN どんどこ |
 中央のシンボルツリーは、子ども達がぶつかっても大丈夫なように柱に緩衝材を巻いてスタッフが作成 |
 スタッフ手作りの段ボール製電車 |
 おままごと用テーブルと椅子も手作り |

窓から見える西武線。子どもが手を振ると運 転手さんが手を振ってくれることも
BOUKEN どんどこは、広いスペースがあるので、およそ6か月未満のねんねの赤ちゃんが過ごせるコーナーのほかに、室内でも体をつかって遊べるすべり台、大型積み木、段ボール製電車などがあります。スタッフ手作りの物が多く、温かい雰囲気です。
また建物が 西武線の横に位置しているため、窓から電車がよく見えるので電車好きのお子さんには絶好のスポットです。一番の魅力は、お子さんが親子ひろばでエネルギーを発散しきれなかったり、室内に飽きてしまったら階段を降りてすぐ外に遊びに行くことができること。これはプレイステーションに併設された親子ひろばだからできることです。
「BOUKEN どんどこを、地域の友達づくりに利用してほしいです。BOUKEN どんどこの隣にある『ふれあい』の部屋が活用されるなど、育児サークル等の活動も広がっていくと良いなと考えています」と塩原さん。
BOUKEN どんどこのスタッフは、全員子育て経験者。利用者の方々からは、「明るい人が多い」「話しやすい人が多い」と言われているそう。スタッフにはカウンセラー、助産師、管理栄養士もいて、ママ達との何気ない 会話から悩み事の相談になったりもするそうです。同じ建物内に相談室があるので個別に相談することも可能です。
OPENして1年目なので、まだ地域のイベント等には参加していませんが、これから、地域の様々な活動に参加したいとのこと。来年度はプレステまつりも行う予定だそうです。
塩原さんより「新型コロナウイルス感染症対策のため、今は、時間制限と人数制限があり、 食事はできず、ご不便をおかけしています。どなたでも気軽に遊びに来てください。2 階のBOUKEN どんどこでも、1 階の部屋でも、外でも遊べます。動きやすい服装で来ることをお勧します」とのことです。(2020 年 10 月現在)
塩原さんのぶんハピ 国分寺歴40年以上

ひろば責任者の塩原真有美さん
花沢橋近くの線路沿い遊歩道
電車好きの息子とベンチに座ってお団子を食べながら、よく電車を眺めました。息子が幼かった頃の良い思い出の場所です。
取材:ぶんハピリポーター

子連れのぶんハピポイント
幼児用のトイレや立ったままオムツ替えができるコーナーがあります。
 おむつ替えコーナー 緑扉奥は幼児トイレ |
 トイレ前のピンクのマットは立ったままオムツが替えられるコーナー |
 授乳室と保温ポットがある調乳室も |
 右奥が授乳室、カーテンやドアを閉めて利用できます |
基本情報BOUKEN どんどこ 住所:国分寺市東戸倉 2-28-4 TEL:042-323-8550 開場日時:火曜日~土曜日(月・日・祝日は休み) 10:30~12:30 14:30~16:30 ※2020年10月現在、親子、スタッフあわせて18名まで入室可能(6か月未満児は人数に入れない)新型コロナウイルス感染症の状況によって変更する場合があります。ご利用前にホ ームページをご確認ください。 ホームページ:www.boukenasobibanokai.or.jp |
|
●チェックポイント   
*幼児用トイレ、駐輪場あり、駐車場無し(近くにコインパーキングあり)
|
|


 保管・管理の都合上、終了時間まで残った場合、終了後にご連絡致します。お引き取り頂けるようお願いします。
保管・管理の都合上、終了時間まで残った場合、終了後にご連絡致します。お引き取り頂けるようお願いします。





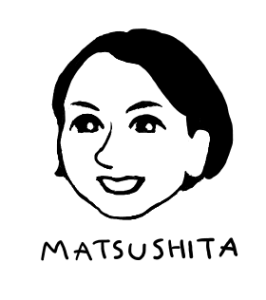

 ①手続き:あずこっこクラブの登録は、BOUKENたまごの利用時にスタッフへ登録したい旨を伝えて、登録シートに必要事項を記入します。登録してあずこっこクラブカードを受け取ります。(あずこっこクラブデイでも登録して、参加が可能)
①手続き:あずこっこクラブの登録は、BOUKENたまごの利用時にスタッフへ登録したい旨を伝えて、登録シートに必要事項を記入します。登録してあずこっこクラブカードを受け取ります。(あずこっこクラブデイでも登録して、参加が可能)